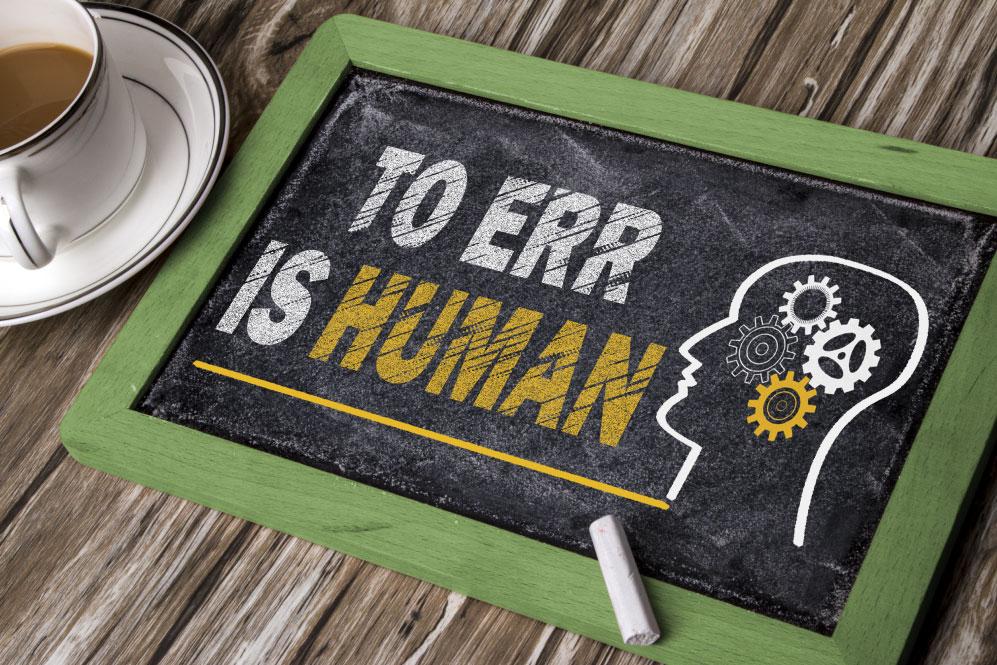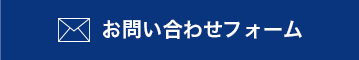コロナ禍のハイブリッドイベントを企画から徹底サポート。
豊富なノウハウと“寄り添い力”でトラブルも迅速に解決
事例のポイント
1.コロナ禍に最適化したイベントを企画から提案
2.通信インフラ未整備の会場でもレジリエンスな配信・中継システムを構築
3.あらゆる事態を事前に想定することで予測不能なトラブルにも迅速に対応
■団体紹介
2020年5月にケニアのサッカークラブの指導者からのSOSをきっかけにスタートした緊急支援プロジェクト「A-GOALプロジェクト(Africa-Global Assist with Local Sport Clubs)」が発端。
アフリカ現地の「地域スポーツクラブ」を拠点に食糧支援・感染症予防支援を実施した。2021年6月に一般社団法人となった。
代表理事の岸卓巨さまは、大学時代にバヌアツ共和国で村人を対象としたサッカーイベントを主催したのち、2011年からは青年海外協力隊としてケニアで活動。

現在、日本アンチ・ドーピング機構に所属しつつ、A-GOAL代表理事としてアフリカ各国と日本をスポーツで繋ぎ、持続可能な社会を目指すさまざまな活動を行なっている。
インタビューにご協力いただいた方

一般社団法人A-GOAL
代表理事 岸 卓巨 様
(写真・中央)
濱野 大志 様
(写真・左から2番目)
NTTビズリンク株式会社
ビジネスソリューション本部
ソリューションエンジニアリング部
須永 健治(写真・左側)
中村 龍(写真・右から2番目)
ビジネスソリューション本部
セールスエンジニアリング部
遠山 美霞(写真・右側)
【導入の背景・課題】
・会場1カ所のリアルイベントを予定していたが、コロナ禍の感染者数が急増。イベント企画の見直しが急務
・オンライン配信はリソース不足でいったん断念していたため、ハイブリッド開催をするならば協力事業者が必要
【導入後の効果、期待】
・会場を小分けにして「密」を回避。会場が分かれることで一体感の欠如が懸念されたが、巧みな映像スイッチングで防止。
・カメラはボランティアの自前のスマホを活用するなど、限られた予算に対応しつつ高い映像品質を実現。海外からのオンライン参加者だけでなく、後日のアーカイブ配信も好評。
・ネット回線のない会場だったが、LANケーブルを100メートル以上引くなど豊富なノウハウを生かして配信・中継システムを構築。途中の接続トラブルはスマホのテザリングで乗り切るなど、不十分な環境でも「途切れない配信」を実現。
・撮影に学生ボランティアが参加。決まった時間内で目指す表現をつくりあげる体験が「チームビルディング研修」にも役立つと発見。複数拠点をつないだ配信のあり方も含め、ハイブリッドイベントの新たな可能性を創出。
コロナ感染拡大で開催内容の見直しを迫られる
・アフリカへの関心を広げる機会としてイベントを企画
・オンライン開催には予算も人手もノウハウもなかった
遠山:
NTTビズリンクの「映像・イベント配信ソリューション」は、お客さまのニーズに徹底して寄り添うのが特長です。企画・設計から中継・配信システムの構築、当日の運用や各種サポートまでワンストップでご提供しています。
今回は、コロナ禍でのハイブリッドイベント事例として、2022年8月に開催された「Africa Action Day2022」をご紹介します。ちょうど「第7波」がピークを迎えるタイミングで、当初の企画を見直す必要が生まれ、予定になかったオンライン配信も追加したハイブリッド開催となりました。その経緯と、どのように変化に対応していったかを、A-GOALのお二人に振り返っていただきつつ、現地でサポートしたNTTビズリンクのメンバーにも話を聞きたいと思います。まずA-GOALの岸さまと濱野さま、「Africa Action Day2022」の概要について教えてください。
岸:
私たちA-GOALは、スポーツを通じて日本とアフリカをつなげ、持続可能な社会をつくるというのをテーマに活動しています。「Africa Action Day2022」は、3年に1回開催される「アフリカ開発会議(TICAD)」に合わせて、広くアフリカへの関心を広げる機会をつくりたいと考えて企画しました。
濱野:
コロナ禍が長期化する中で「リアルな交流の場をつくりたい」という思いもありました。もちろん感染防止対策を徹底しながら、可能な範囲で体を動かしつつ、子どもから大人まで世代も個々の興味も超えて楽しめるイベントにしたかったんです。
岸:
そのため、当初はイベントをオンライン配信するつもりはありませんでした。リアルな場を大切にしたいという気持ちが強かったですし、予算や人手も限られていました。オンライン配信のためには機材やスタッフを用意するだけでなく、集客方法も検討しなければなりませんから。

しかし、「コロナ第7波」の到来で軌道修正を余儀なくされました。当初は会場施設の体育館のみで開催する予定でしたが、感染拡大防止の観点から大人数が1カ所に集まるのは避けなくてはなりません。入場人数やプログラムの数を縮小して開催することも視野に入れ始めたとき、NTTビズリンクさんと出会ったのです。頭の片隅で、ハイブリッド開催をするなら配信事業者さんを探す必要があると思っていましたので、非常にタイムリーでした。
ネット回線のない会場でも配信・中継システムを構築
・メイン会場の体育館はネット回線がなく、地下のため電波も届かなかった
・質量ともに充実したプログラムを適切に配信
遠山:
オンライン配信とのハイブリッド開催をするには厳しい環境だったと聞いています。具体的にはどんな状況だったのでしょうか。
岸:
まずNTTビズリンクさんに、会場を複数にして配信でつなぐというアイデアを提供いただきました。会場にはセミナールームなどもありますので、同じビルの中でそれは実現可能でした。ただ、メイン会場の体育館は施設側から「オンライン配信は難しい」と言われていたんです。
中村:
現地で見てみると、ネット回線自体が体育館にありませんでした。しかも地下にあるため、携帯電話の電波もほぼ届かなかったのです。
須永:

細かく調べていくと、1フロア上の1階の会議室にネット回線が通っていることがわかりました。幸い、スピードも早い優良な回線でしたので、そこから地下までLANケーブルをつなぐことにしたのです。
まさに人海戦術で、床にケーブルを這わせていきました。結局100メートルほどの長さになりましたね。
岸:
私には全く思いつかないアイデアで、さすがは通信に圧倒的な強みを持つNTTグループさんだと感心しました。会場を分散したことで、正直に申し上げると、求めていたイベントの一体感が失われるのではないかという懸念もあったんです。それどころか、小さな部屋だと孤立感を生んでしまうおそれもあると思っていました。でも、有線のLANケーブルやWi-Fiを駆使して配信・中継システムを構築し、一般向けだけでなく、各会場にもそれぞれの映像を届けるようにしてごく自然に一体感が得られるようにしてくれたのはありがたかったですね。
中村:
複数拠点を配信でつなぐのは今までも経験してきましたが、プログラムが非常に充実していましたので、弊社にとっても大きなチャレンジではありました。パラスポーツゲームの「ボッチャ交流会」やアフリカンドラム・アフリカ布の「体験型ワークショップ」、アフリカとも中継でつないだトークショーなど、質量ともにぎっしり詰まっていて、貴重な体験をさせていただきました。

イベント趣旨も理解した臨機応変なサポートで品質向上に貢献
・学生ボランティアが自前のカメラで撮影し、Zoomで接続
・「チームビルディング研修にも最適」という発見
・あらゆる事態を事前想定しているため、迅速な対応が可能
遠山:
予算と人手が限られているというお話がありましたが、撮影は運営ボランティアにおまかせし、“ぶっつけ本番”に近い形で行われたそうですね。
須永:
はい。テレビの中継などでは、専用のカメラで撮りながら電波で飛ばすのが一般的ですが、やはりそれなりのコストがかかります。そこで、ボランティアさんの自前のスマホを使って、撮影した画像をZoom経由で配信しました。驚いたのは、彼らが想像以上に適応していたことです。撮影しながらリポートをしてもらったのですが、テレビ顔負けの内容でした。
濱野:
ボランティアが撮影した映像をダイレクトに配信するのは少々不安でした。その点、NTTビズリンクさんが巧みにスイッチングしてプロの品質を保ったまま流してくれたので、安心感がありました。

また、私自身新卒1年目でいろいろな研修を受けているのですが、決まった時間内で目指す表現をつくりあげていくプロセスはまさに「チームビルディング研修」だと感じました。実際、ボランティアとして参加した学生の満足度も非常に高かったので、オフィス内で座学の研修を受けるより、実際の現場で体験を通じて学べることがたくさんあるのではないでしょうか。
遠山:
社員研修だけでなく、イベントと組み合わせたキャリア教育として、職業体験に活用いただくのも良さそうですね。イベント開催中のNTTビズリンクの現場対応はいかがでしたか?
岸:
イベントは生き物のようなものですから、マイクの位置変更など、前置きなしにいろいろなことをお願いしました。無茶なことも申し上げていたと思いますが、嫌な顔ひとつすることなく、臨機応変に対応していただきました。多数の経験を積んでこられたことが伝わりましたし、イベントの趣旨を深く理解してくださっていることがわかるご提案も都度いただいて、「寄り添い力」の強さが非常に頼もしかったですね。
須永:
ありがとうございます。私たちが現場対応で常に意識しているのは、「お客さまのご要望には可能な限り応える」です。
「できません」と断るのは簡単ですが、そうするとイベントの運営にも影響が出るでしょうし、主催者の方が望む演出もできなくなると考えています。
今回でいえば、岸さんにはイベントのチェアマンとしての役割がある上、トークショーではモデレーターもされていました。そういった部分に集中いただけるように、テクニカルな部分は全ておまかせいただけるようにしようとの想いがありました。
中村:
お客さまの要望に応えるため、現場対応のチーム全体であらゆる事態の想定を共有するようにしています。
例えばマイクの位置を動かしたら、他のどこにどんな影響が出るのか、できるだけシミュレーションを重ねるようにしています。

深刻なトラブルも“さりげなく”復旧させる現場対応力
・オンライン配信で禁忌ともいえる「途切れ」が発生
・参加者にトラブル自体を気づかせない迅速なトラブルシューティング
・アーカイブを残せることもハイブリッドイベントのメリット
遠山:
しかし、どれだけ入念に準備をしても、イベントにはトラブルがつきものです。今回のイベントではどんなトラブルが起き、どう対処したのでしょうか。
岸:
ごく短時間ですが、あるステージプログラムで配信が途切れてしまいました。実は今回のオンライン配信の中には有料プログラムがあったのですが、そのひとつだったので焦りました。ところが、NTTビズリンクさんの対応は終始冷静でした。テクニカルな部分の対応をしながら、イベントの進行を少し遅らせるようご指示いただき、すぐに復旧することができました。おっしゃるように、あらゆる事態を想定して準備をしているからこそ、迅速なトラブルシューティングが可能なのだと思います。
須永:
配信が途切れたのは、1階から引き込んだケーブルがネットワークにつながらなくなったからです。想定はしていたので、すぐにスマートフォンのテザリングに切り替えました。地下だと電波につながりにくいので、事前につながることを確認しておいた階段の途中でスマートフォンを掲げていました。
濱野:
通常のテザリングでもおそらくは大丈夫だったかと思いますが、“落ちない”ように帯域を下げて負担を下げる工夫もしました。
岸:

イベントを開催する側からすると、配信が途切れるといったトラブルは極力回避したい。そうすると、得てして「トラブルが起こりそうだからチャレンジは控えよう」となってしまいます。このような消極的な姿勢と、「トラブルが起きても何とかなるからギリギリまでチャレンジしよう」という積極的な姿勢では大違いですよね。NTTビズリンクさんは、どんなトラブルでも何とかしてくれるので、思う存分チャレンジできます。
こうやって複数の拠点をつないで配信できることがわかったので、今回は日本人向けのイベントでしたが、今後は、アフリカの子どもたちに日本の情報を届けて楽しんでもらえるような企画を考えたいですね。
遠山:
ありがとうございます。単にリアル開催のオンライン版を配信するのではなく、さまざまな取り組みをつなぎ合わせて世界中がシームレスに楽しめるプログラムに仕上げることで、ハイブリッドイベントの価値が高まると改めて気づかされました。
岸:
そう聞いて気づきましたが、アーカイブを残せるのも非常に魅力的だと感じました。今回のイベントはYouTubeで配信していますが、空間だけでなく時間を越えて楽しめるのはいいですね。
私自身、当日はオンライン配信が見られなかったので、アーカイブを見て「こんなに工夫して配信してくれたんだ」と思いました。
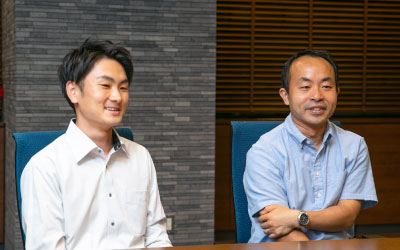
あとからの振り返りにも役立ちますし、NTTビズリンクさんにハイブリッド開催のご提案をいただいて本当によかったです。今後もぜひ、イベント開催の際は企画段階からご相談をさせてください。