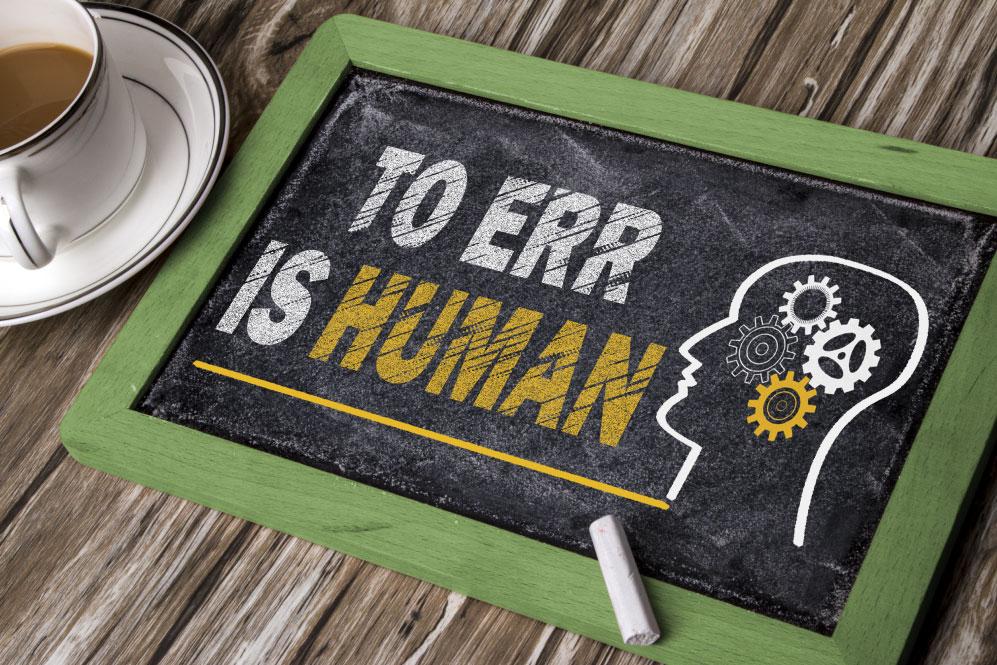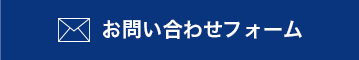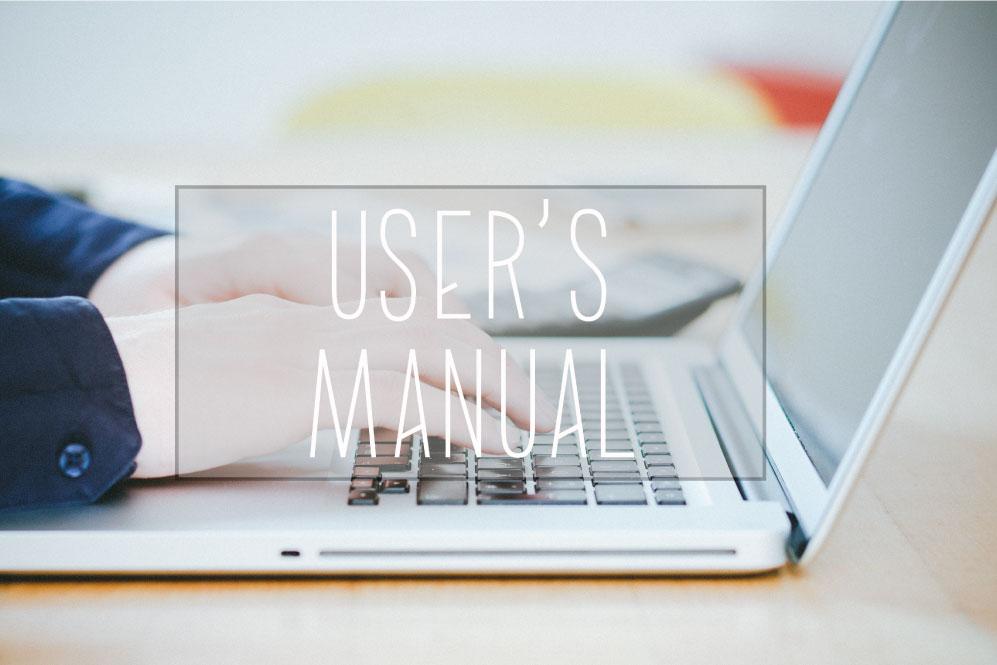
コールセンターは、どのスタッフが対応しても一定の品質を保ったサービスを提供しなければなりません。そのためには、しっかりとしたマニュアルが不可欠といえます。マニュアルは業務中の参考になるだけでなく、新しいスタッフの教育や引継ぎ資料としても有用です。
この記事では、コールセンターにマニュアルを作るメリットや、作成前の準備、作成と運用の手順について詳しく解説します。よりよいマニュアルにするための重要ポイントも紹介しています。ぜひ、マニュアル作りに役立ててください。
目次
1.マニュアルとは?作る目的は?
2.コールセンターでマニュアルを作成するメリット
3.マニュアルの作成前に準備すること
4.マニュアルの作り方・運用の手順
5.マニュアルを作るときのポイント
6.まとめ
1.マニュアルとは?作る目的は?
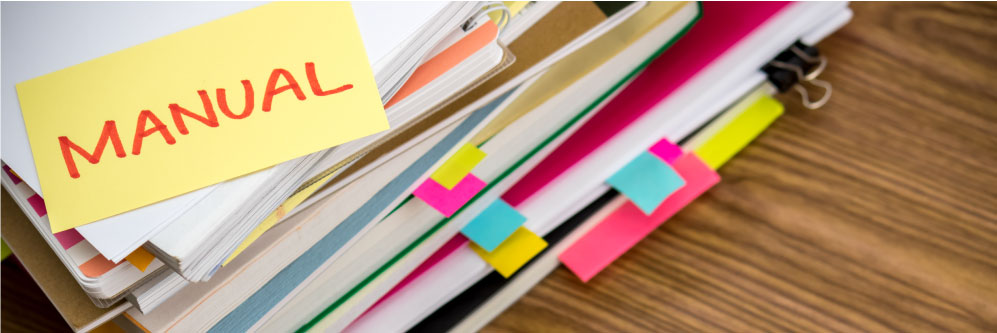
マニュアルとは、業務を正しくスムーズに行うための具体的な手順を記した資料です。解決法を見つけやすいよう、目次やカテゴリー分けなどで解説を体系化しているという特長があります。マニュアル作成の目的は、読む人に業務の全体像を把握させて業務への理解を深め、業務品質を上げることです。
2.コールセンターでマニュアルを作成するメリット

コールセンターでマニュアルを作成するメリットは、コスト削減や品質アップなどがあります。具体的に解説します。
教育・指導に割く時間を短縮できる
マニュアルは、指導係の代わりを務めるものです。口頭のみで教育した場合、説明や理解のスキルにばらつきが出やすく、繰り返し教える必要も出てきます。マニュアルがあれば、理解のスピードに合わせて読みこめるため、手順を覚えやすくなるでしょう。
引継ぎ資料として利用すると、教える側・引継ぐ側、両者の負担を減らせます。作業中に参照することもでき、指導係に確認する手間を省けることもメリットです。
コストが削減できる
口頭での教育は、教える側と教わる側両方の時間コストがかかってしまいます。効率が悪いため、場合によっては残業代など人件費がかさむこともあるでしょう。マニュアルがあれば時間コストが少なくなるので、人件費の削減にもつながります。
個人に依存するリスクを減らせる
業務によっては「担当者しか知らない・できない」など、個人に依存しているものがあります。こういった状況は、担当者の退職・休職などで、その業務が滞るリスクをはらんでいます。そういった業務をマニュアル化しておくと、担当者が不在のときも他のスタッフがカバーでき、業務が正常に回るようになります。
商品やサービスの品質維持につながる
マニュアルなしで業務を行うと、オペレーターの経験やスキルによって対応の品質がばらつき、顧客に均一のサービスや商品提供を行えません。また、ノウハウが体系化されず、作業もれなどのミスが起こりやすくなります。マニュアル作成は、正確で安定したサービス提供に貢献し、顧客満足度アップにつながります。
3.マニュアルの作成前に準備すること

準備をしっかりしておくことで、わかりやすく高品質なマニュアルを効率良く作れます。以下のポイントを意識して、マニュアル作成の準備をしましょう。
マニュアルの管理・運用担当者を決める
高品質なマニュアルのポイントは、作成したら終わりではなく、引き続きブラッシュアップしていくことです。修正や補足などが後回しにならないよう、管理・運用の担当者をあらかじめ決めておきましょう。
誰を対象にしたものか明確にする
作成するマニュアルの対象者を明確にすると、理解しやすいマニュアルが作れます。たとえば、新しいスタッフ向けにマニュアルを作成する場合、シンプルな構成で専門用語を少なくし、初歩的な予備知識も入れるなどの配慮が必要となるでしょう。
用途・どのシーンで使うかを確認する
マニュアルは、業務のノウハウをすべて詰め込むのではなく、用途や扱う業務範囲を明確にして作成しましょう。範囲が広くなりすぎると、作成者と読む側の双方に負担がかかってしまいます。作成や読み込みに時間がかかれば、マニュアルによる業務効率化が先延ばしになってしまい、部署全体の損失になりかねません。
いつまでに作成するか期限を定める
マニュアルなしで業務が行われている場合は、作成が後回しになりやすいです。まずは作成期間、完成時期、配布時期などの目標を決めて、作成に取り掛かりましょう。扱う業務の難易度が上がるにつれて作成時間がかかるため、現実的なプランをたてることがポイントです。
マニュアルに適したフォーマットを決める
マニュアルごとにWordやExcel、PowerPointなど適したフォーマットを選び、以後はそのフォーマットで作成を統一しましょう。作成側が情報を整理・修正しやすく、読む側も情報を探しやすくなります。文章が中心であればWord、表・リストを多用するならExcel、音声やアニメーションを使うならPowerPointが適しているでしょう。
マニュアルを始めとしたとしたコールセンター改善なら、NTTビズリンクのコンタクトセンターソリューションをお問い合わせください。
4.マニュアルの作り方・運用の手順

体系的にマニュアルを作成することは、読む側がわかりやすくなるだけでなく、作成者も作りやすいです。作り方を時系列でまとめました。
マニュアルに入れる内容を決める
マニュアルに入れる内容を決めるために、業務の洗い出しを行い、業務全体を可視化します。業務内容や現在・今後起こりうる問題、業務で求められるスキルレベルを明らかにすることで、マニュアルに盛り込むべき項目が自ずと決まります。
カテゴリーごとに分類する
点在状態の項目をカテゴリーごとに分類し、おおよその体系を作ります。なにもかもをマニュアルに詰め込むとわかりにくくなるため、必要な項目かを検討しながら分類します。
全体の構成(目次)を決める
目次などの構成を決めておくと、どこに、どの範囲までの内容を盛り込むかはっきりします。内容が冗長にならず、情報も探しやすくなるでしょう。作業内容を時系列に沿って並べると、全体の流れを具体的に把握でき、わかりやすくなります。また、担当者ごとに分けると、誰が、いつ、何をすべきかを把握できます。
仮マニュアルを作る
構成をもとに、まずは仮マニュアルを作ります。上司などに内容を確認してもらい、意見や改善案を聞くと、より良いマニュアルになるでしょう。さらに、仮マニュアルを使って実際に作業をしてみます。作業をしていくうちに、足りない項目や改善ポイントなどが明らかになるので、ブラッシュアップを繰り返していきましょう。
チェックリストを作成する
作業手順を確認するチェックリストを作っておくと、よりわかりやすいマニュアルになります。チェックリストは簡易的なマニュアルにもなるうえ、ミスがないかを確認するツールにもなり、業務の正確性アップにつながります。
マニュアルを共有する
ここまでマニュアルが出来上がったら、対象者に配布します。必要なセキュリティ性などを鑑みて、紙やデータで配布するのか、オンライン閲覧にするのか、上司の指示などを仰ぎ、事前に決めた方法で配布しましょう。
マニュアルを使って作業を行ってみる
いよいよマニュアルの運用開始です。作成したマニュアルに沿って、対象者に業務を行ってもらいます。
フィードバックを収集する
実際の業務で運用すると、わかりにくいところや内容のもれ、改善案など、いろいろな意見が出てきます。もれなくフィードバックを収集できるようにミーティングの場を設けて、積極的に聞き取りを行いましょう。
改善点をふまえてマニュアルを更新する
集まったフィードバックをもとに、マニュアルを更新します。どこを更新したのか、対象者に周知することも重要です。
定期的に見直し・改訂を行う
マニュアルは、管理・運用担当者が定期的に更新しましょう。自社の方針や現場状況の変化など、新しい状況に沿うよう注意します。現場とのコミュニケーションを日頃から取ることもポイントです。
5.マニュアルを作るときのポイント

覚えやすく、予期せぬ事態にしっかり対処できるマニュアルを作るためのポイントを解説します。
仕事の全体像を記載する
仕事の全体像を記載しておくことは、業務の品質アップに重要です。全体像を把握できれば、自分がしている作業の目的や、全体の中でどんな役割を果たすのかが理解でき、的確で判断の早い作業につながります。
手順だけではなく「理由」や「目的」を明記する
マニュアルには、手順だけではなく「なぜ」「何のために」そうするのかを明記しましょう。手順だけの解説では重要度や優先度がわからず、状況によっては省略されてしまうなど、オペレーターの対応品質にムラができる原因となるからです。
さまざまなケースに応用がきく判断基準を入れる
日々の業務では、マニュアルだけではカバーしにくいケースが生じます。オペレーターがマニュアルを応用して対応できるよう、判断基準も記載しておきましょう。たとえば、過去のケースとその対応策の項目を盛り込むと、類似ケースへの応用の助けになります。
写真・イラスト・図などを挿入する
業内容によっては、文章だけではなく、写真やイラスト、図を取り入れるようにしましょう。文章だけでは具体的にイメージしにくい操作や業務フローも、画像や図になると情報が視覚化され、頭に入りやすくなります。
重要な部分を強調する
フォントの色やサイズなどを変えて、重要な部分を強調することもポイントのひとつです。同じフォントでの長い文章は冗長に感じ、ポイントを取りこぼしやすくなります。しかし、重要な部分が目立つように配慮すると集中力の喚起に役立ち、記憶しやすくなるでしょう。箇条書きを利用することも、要点を強調するいい方法です。
トラブル・クレーム時の対応方法・事例を入れる
ミスやクレームなどのトラブルが起きた際の対応方法や事例を盛り込んでおくことも大切です。クレームの事例やミスへの対応方法がわかっていれば、同じトラブルが起きないように注意して対応できます。また、オペレーターのプレッシャーが軽減され、冷静に対応できるでしょう。
6.まとめ
コールセンターでは、どのオペレーターが対応しても応対品質が保たれていることが重要となります。上記でご紹介したマニュアル作成は応対品質の標準化には不可欠な要素といえますが、作成されたマニュアルが適切に運用され、すべてのオペレーターが不安なく応対できることがコールセンターの目指すべきところです。作成したマニュアルの効率的な習熟、運用のモニタリングには、音声をテキスト化し提供してくれるチャットシステムの活用が効果的です。
NTTビズリンクのコンタクトセンターソリューションは、AIチャットと有人応対チャットの連携が可能であり、特にオペレーターの習熟、応対モニタリング業務をお手伝いします。AIチャットから有人応対チャットへの切り替え、オペレーターからスーパーバイザーへの引継ぎ、Web・電話といった複数の窓口を1つのシステムで管理できる機能、それらをテキスト化したデータを残すなど、コールセンターの現場即戦力となる機能が充実しています。