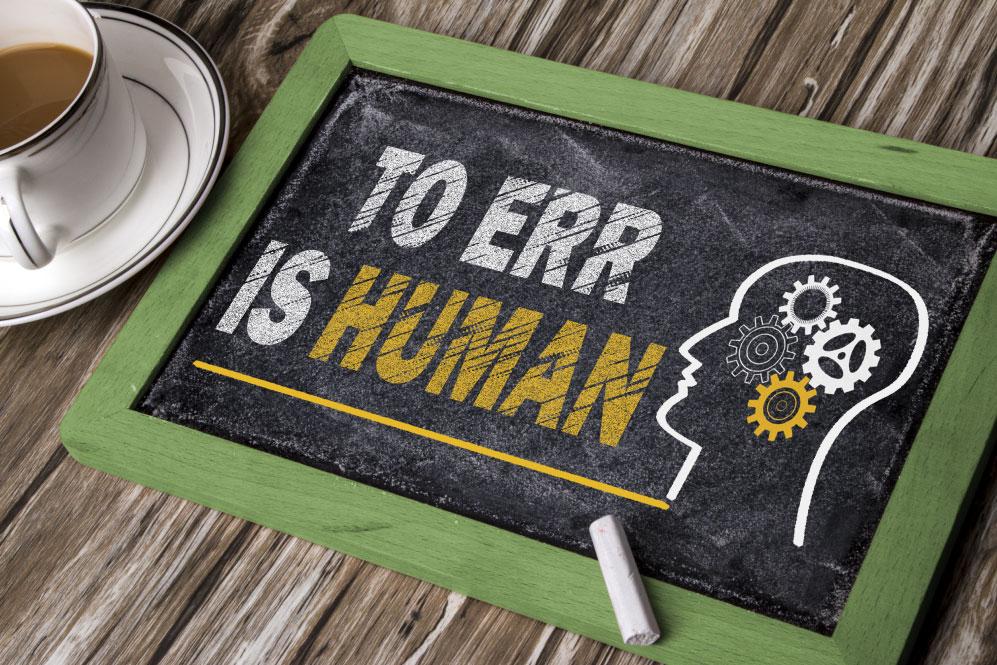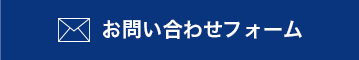コールセンターは個々の電話対応がメインなので、業務を効率化しにくい面があります。業務効率化でコスト削減を達成したいものの、どの方法が適しているのか、何から取り組むべきかわからない場合も多いのではないでしょうか。
この記事では、コンタクトセンターにおける業務効率化のメリットや方法を具体的に多数紹介します。また、施策を実行する際の注意点や押さえておきたいポイントも解説します。ぜひ、業務効率化に役立ててください。
目次
1.業務効率化とは?
2.業務効率化をするメリット
3.業務を効率化させる方法
4.業務効率化を進める際に注意すること
5.業務効率化をする際のポイント
6.まとめ
1.業務効率化とは?
業務効率化とは、言葉のとおり業務を効率的に行うことです。集団活動としてみた場合は、全人員の能力を十分に活かし切ることといえます。負荷が多すぎる「ムリ」、負荷が少なすぎる「ムダ」、ムリとムダがランダムに現れる「ムラ」をなくすことが、業務効率化の基本と考えられています。
「生産性向上」との違い
業務効率化と生産性向上は、混同されがちです。生産性向上の意味は、「少ない労力で多くの成果を生み出すこと」なので、成果にフォーカスがあてられています。つまり、手段と目的のどちらに焦点が当たっているのかが、2つの言葉の違いといえるでしょう。
2.業務効率化をするメリット
業務効率化を進めることで、どのようなメリットがあるのかを解説します。
人件費などのコストを削減できる
業務効率化によってムリな作業がなくなれば、残業や休日出勤などが減って、人件費を削減できます。そのほかにも、お問い合わせ窓口を統合して設備費を削減することもできます。
オペレーターの負担を軽減できる
業務効率化でムリな作業が少なくなると、オペレーターの肉体的な負担を減らせます。また、短時間で顧客対応しなければならないなどのプレッシャーも少なくなり、業務におけるストレスを減らすこともできます。
収益アップが期待できる
業務効率化によるコスト削減は、企業の利益向上につながります。また、作業時間が減ることで、オペレーターは、より注力すべき応対に時間を費やせることが可能になるでしょう。それにより、さらなる収益アップにつながります。
優秀な人材の流出防止・確保につながる
間接的なメリットでは、優秀な人材の流出防止や確保につながることが挙げられます。業務の負担が減ったことで、会社への信頼度が高まり、モチベーションを持って働いてもらえるようになる事例も多いからです。
また、収益向上により、給与アップや福利厚生の充実も図れるため、優秀な人材の確保にもつながるでしょう。

3.業務を効率化させる方法
業務効率化を実現するための方法について、具体的に紹介します。
業務マニュアル・フローチャートを作成する
業務マニュアルやフローチャートは、特に経験が少ないオペレーターにとって重要です。こうした書類が整っていないと、無駄な作業が多くなってしまいます。
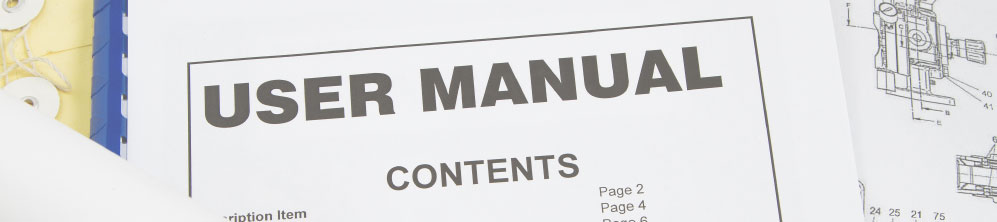
作成のポイントは、わかりやすさや検索性を重視することです。網羅性を優先させてしまうと、どこにどんな情報があるのかわからず、役に立たないケースもあるので注意しましょう。
定型業務を自動化する
機械的に行っている業務を自動化すれば、作業時間を短縮できます。
Excelのマクロ機能で自動化する方法
入力項目の転記やある操作を完了した際に日付を記入するなど、決まった作業はExcelのマクロ機能で自動化できます。簡単なボタン操作であれば、その作業を一連の操作として記録・登録が可能です。
RPAを導入する方法
RPAは「Robotic Process Automation」の略で、入力項目のチェックや金額の合計を求めるなどの定型業務を代行するソフトウェアのことです。よく使う機能がパッケージ化されているので、比較的簡単に業務の効率化ができます。
AI技術を活用する方法
AI技術を活用すると、人が対応するような業務を自動で行えるようになります。AIが代替できる領域は幅広くありますが、取り扱いに専門知識が必要なものもあるためどんなAIを使うのかは精査が必要です。
顧客対応はチャットシステムを使う
顧客対応にチャットシステムを使う方法もあります。一般的なお問い合わせなどの定型業務をチャットボットが対応すれば、オペレーターの業務を軽減できます。顧客がより深い情報を知りたくなったときはオペレーターに転送するなど、ハイブリッドで活用できるタイプもあります。
AI技術を活用する方法
職場環境の改善でも、業務効率化は可能です。
リモートワークの導入
コールセンターのオペレーター業務をリモートワーク(在宅勤務)にする企業が増えています。オペレーターは通勤の必要がなくなり、企業は事務所の費用や交通費を削減できます。

オフィスレイアウトの変更
オフィスのレイアウト変更も、業務効率化につながることがあります。動線(通路)を効率的に確保し、職場内の移動を効率化すれば、業務も円滑に進むようになります。
オペレーターのスキルアップを図る
社内教育によるオペレーター一人ひとりのスキルアップも、業務効率化の一つの方法です。パソコンやツールの使い方、リーダーシップ研修などは、それらの教育に特化した外部機関を利用すると効率的です。

適性や保有スキルに合った人員配置にする
オペレーターの得意・不得意や保有スキル、経験などに応じて人員を再配置することも、業務効率化につなげる方法です。適切な人員配置により、業務がスムーズに進むようになります。
また、仕事量を調整したり、インセンティブを付与したりするなどして、オペレーターのモチベーションを高めることも重要です。

4.業務効率化を進める際に注意すること
業務効率化を進めるうえで、どのようなことに注意すればいいのかを挙げていきます。
業務や目的に合った手段を選ぶ
業務内容や目的・目標に応じて、最適な手段を選択することが大切です。目的に対して手段が合っていないと、部分的に効率化できてもトータルでは手間やコストがかかることも考えられます。
効率重視でサービスの質を落とさない
効率を重視するあまり確認作業を省略すればミスが増えますし、応対時間を短くしようと早口で話せば顧客からクレームを受けてしまうかもしれません。効率を重視するあまりサービスの質が落ちるようなことは、ないように注意しましょう。
一度に複数の方法を取り入れない
一度に複数の方法を取り入れると、現場が混乱してしまいます。また、どの施策が効果的だったのかも確認しにくくなるでしょう。現実的に実行できるプランを考えて、一つずつ実行していくことが大切です。

5.業務効率化をする際のポイント
職場の人たちと協力して業務効率化を進めていくポイントを、計画から実施までの流れに沿って紹介します。
目的や目指す方針を定めて共有する
まず必要なことは、目的や目指す方針を決め、企業やチーム内でそれを共有することです。この方針にブレがあると、どの作業を削除すべきか、何を優先させるかなどの判断ができません。
業務の洗い出しを行う
方針が決まったら、業務の洗い出しを行います。業務内容を明確に把握することで、削除すべき業務と残すべき業務を区別できます。具体的にどのようなことを行っているか、時間帯ごとに書き出してみましょう。
現場の声を聞く
実際に業務を担当しているオペレーターに、意見を聞くことも重要です。日ごろ感じている不満を解決することで、大幅な業務改善ができるかもしれません。また、改善提案も貴重な意見であることが多いといえます。
体制を整えタイミングを見定めてから実行する
業務効率化の施策を実施する前に、十分な教育を行ったり、業務フローを作成したりするなど、体制を整えるようにしましょう。また、実施開始日はベテランオペレーターが多く在籍する日を選ぶ、閑散期を選ぶなど、タイミングを図ることも重要です。
業務改善のフレームワーク「ECRS」を用いる
業務改善を検討する際には、「ECRS(イクルス)の原則」を活用しましょう。ECRSの原則は、業務改善のための手順を教えてくれます。
「Eliminate(排除)」
ECRSの原則では、必要のない業務の排除から始めます。ペーパーレス化や転記作業の自動化を取り入れて、無駄をなくしましょう。
「Combine(統合・分離)」
Eliminate(排除)の検討が終わったら、統合や分離をしたほうが効率的になる業務を見つけます。たとえば、ルーティン化できる業務をアウトソーシングにすることなどです。
「Rearrange(入れ替え・代替)」
Eliminate(排除)、Combine(統合・分離)が終わった段階で、各業務を見直し、効率化のために再設計できるところはないかを検討します。業務フローの効率化や、適材適所にオペレーターを配置することなどです。
「Simplify(簡素化)」
業務改善の施策を実施したあとで、実施の成果を評価するとともに、さらに簡素化して業務を改善できないか検討します。たとえば、通話応対をチャットシステムに置き換えることなどです。
実行後に効果を検証する
業務効率化を実行した後は、効果を検証することが重要です。サービスの質が低下していないか、一部のオペレーターや部署に負担が増えていないか、効率を重視しすぎてミスが増えていないかなどを確認します。オペレーターの稼働率、残業時間なども評価しましょう。

6.まとめ
業務効率化が実現できれば、生産性が高まり、収益アップにもつながります。マニュアル類の整備や社内教育、AIツールの導入、アウトソーシングなど、現状に合わせて実施していきましょう。
NTTビズリンクには、業務効率化をサポートするためのソリューションがあります。例えばビズリンククラウドCTIはオペレーターの業務を見える化し、適正配置をすることで、効率化につなげることができます。また、ビズリンクAIチャットボットなら、応対を自動化することも可能です。ぜひ、コールセンター業務の効率化についてお悩みの方はご相談ください。