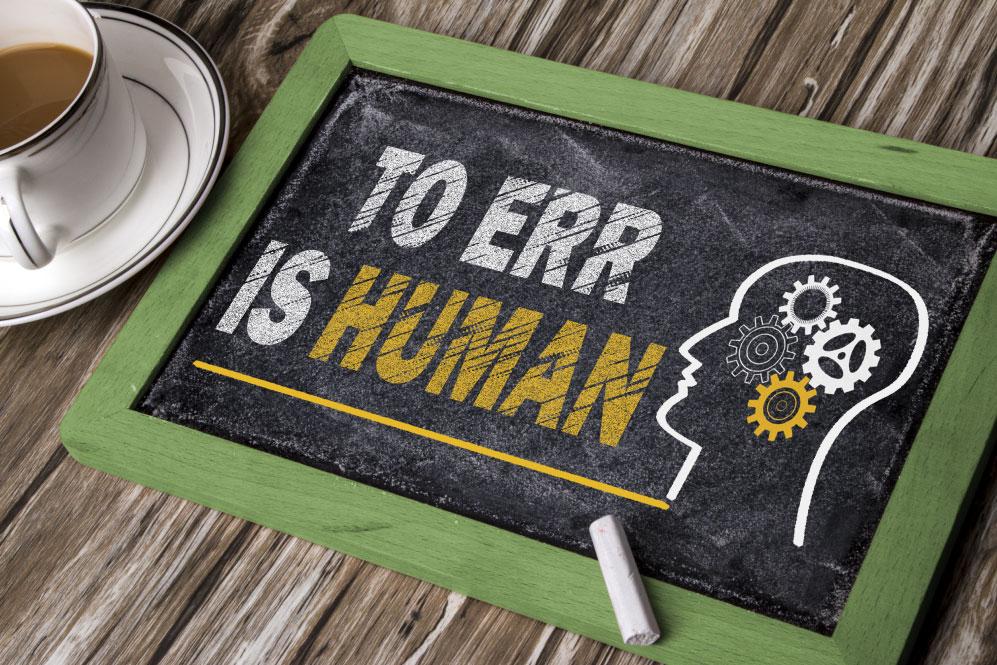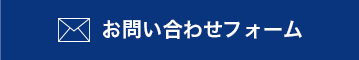少子高齢化が進む昨今、退職による熟練者不足や労働者確保の難化といった問題が深刻になってきています。それに関連し、若い世代への知識・技術の継承といった「知の継承」が思うように進まないことも企業の抱える大きな問題の1つとなっています。
そうした企業において、熟練者・企業側双方の「誤解」がスムーズな継承を阻害する原因となっているケースも少なくありません。こうした中で、「誤解」への対応策を講じて知の継承に取り組んでいる企業もあります。
そこで本コラムでは、知の継承を阻害している課題と、それを解決するための方法について詳しく解説していきます。
目次
1. 知の継承を阻害する課題とは
2. 適切に技術継承を行うための方法とは
3. 「スマートグラス」の導入はNTTビズリンクにご相談を
1.知の継承を阻害する課題とは

①「経験を積めば知の継承ができる(誰でも教えれば習得できる)」と思っている
「経験を積むことで、誰でも知識や技術を習得することができる」、熟練者・企業側のこのような誤解は、知の継承を阻害する要因の1つです。知の継承は目に見えないものなので、正しく伝わったかどうかの判断が難しいものです。
例えば、継承者が作業の本質や全体像を理解していない状態で経験を積んでも、深い理解につながらず、習得に時間がかかってしまうことがあります。類似経験がないと内容を理解するのに時間がかかってしまうのです。
また、作業全体のイメージができていないため、都度その場しのぎの処理を重ね、それが後々トラブルになるおそれもあります。
②「熟練者(伝承者)は、積極的に知の継承を支援してくれる」と思っている
「熟練者(伝承者)は、積極的に知の継承を支援してくれる」、企業側のこのような誤解も知の継承を阻害しているケースの1つです。
熟練者世代の中には、上司などから教えられた経験が少なく、自ら上司などの知識や技術を盗み(学び取り)、自分の糧にしてきた背景を持つ者が少なくありません。熟練者は暗黙知を適切に教える方法を知らないのです。そのため、若手従業員に対してどのように教えればよいのかが分からない、という悩みを持つ熟練者も多いのが現実です。
また業務効率化のため、熟練者が若手を育成する時間がなかなか確保できないという課題もあります。
③「若手(継承者)は、意欲的に知見・ノウハウを吸収する」と思っている
「若手(継承者)は、意欲的に知見・ノウハウを吸収する」と思っているのも、よくある誤解の1つです。
昨今では情報があふれ、先人の築き上げてきたものを何不自由なく手に入れられる環境が整っています。そのため、若い世代の中には「教えてもらうのが当然」といった感覚を持つ受け身の姿勢の者も少なくありません。
また、自分が未熟で自信がないということは理解しているものの、そもそも何の情報や知識が必要かわからないというケースもあります。
④「仕組み(ナレッジDB、マニュアル)を作れば、後はうまくいく」と思っている
「作業マニュアルやナレッジマネジメントなどの仕組みを作れば問題は解消できる」
このように考えている方も多いのではないでしょうか。しかし、こうした考え方も正解とは言い切れません。
例えば作業マニュアルを作成しても、熟練者などが伝えたいことだけが反映されていて、継承者が本当に必要としていることは当たり前のこととして反映されていないケースがあります。仕組みを作っただけでは実際に活用するのは難しいのです。
仮に急いで仕組みを作ったとしても、継承に必要な情報は個人ごとに異なるため、継承者が有効に使える形(その情報を、どの作業の、どういった場面で使うのかを継承者が判断できる形)でなければ、形骸化してしまうおそれがあります。
⑤「企業は、知の継承の取り組みを理解しサポートしてくれる」と思っている
そもそも知の継承の取り組みを理解し、サポートしてくれる企業ばかりではありません。
知の継承よりも、目の前の業務遂行を優先させたり、能力主義による保身が働いたりすることがあります。この場合、実は上司が一番の抵抗勢力なのです。
知の継承には何よりもまず、企業側の理解が欠かせません。
2.適切に技術継承を行うための方法とは

このように、熟練者・企業側の誤解が知の継承を妨げる原因の1つになっています。これらの課題を解決するためには、企業では以下のような取り組みを実行していく必要があります。
①組織に必要な「知」を見極める
熟練者と継承者のスキルを比較することにより、継承者が何に長けていて何が不足しているのかを確認できます。その上で、各スキルの事業に及ぼす影響度と発生頻度などで、継承する「知」の優先順位をつけていきます。
②暗黙知から共有知に変える
経験や勘といった言語化の難しい知識(暗黙知)的作業を客観的に捉え、論理的に説明できる知識(形式知)的作業にすることも大切です。これにより、共通認識の下で誰でもその知識やノウハウを活用できるようになります。その結果、作業品質の標準化や向上につなげることができるのです。
③継承者に作業を行う背景や意味を考えさせる
継承者が作業全体をイメージできるよう、マニュアルや資料、映像などで事前に学習させることも効果的です。その際、「その作業をなぜ行うのか、何をするのか、結果はどうなったか」といったことを考えさせることが重要です。これらを意識させることで、深い理解や素早い習得につながります。
また、指示されたことをするだけでは継承者は育ちません。熟練者と同じように考え、行動できるように育成する必要があります。
④熟練者への支援体制を整える
前述の通り、熟練者世代は上司などから教えられた経験が多くありません。そのため熟練者の中には、若手育成の進め方に悩み、負担に感じる者もいるでしょう。そこで、組織内に継承作業をサポートする場を設け、継承する上で生じた問題点や熟練者の疑問点を解消するなどのサポート体制を充実させることが必要です。これにより、熟練者の負担が軽減し、継承スピードの向上にもつながるのです。
⑤継承者視点で仕組みを作る
また、教わった状況とその知識・技術を使う場面がいつも同じだとは限りません。環境や条件によって、継承者はその都度うまく調整する必要がありますが、初心者である継承者にとっては負担が大きいものです。そのため、相談窓口のような、継承者が抱える悩みや疑問を相談できる仕組みを作ることが重要です。
また、作業マニュアルや資料なども、単なる作業方法の記載にとどまらず、トラブル発生時の対応のようなイレギュラーな処理についても記載しておくことで、継承者が使いやすく、安心感が得られるものとなります。
3.「スマートグラス」の導入はNTTビズリンクにご相談を

知の継承に関しての課題を解決する手段として、デジタル技術の導入を進める企業も増えつつあります。その中でも、近年注目を集めているのがウェアラブルデバイスの1つであるスマートグラスです。
スマートグラスは、熟練者の技術継承を始め、従業員の支援・育成ツールとしても活用されています。そのほかにも業務効率化、生産性向上、DXの推進においても力を発揮しているのです。
一方、続々と新しいスマートグラスが発売されているため、多くの種類・多彩な機能から自社に合ったものを選定することは容易ではありません。そのため、導入から運用まで幅広くサポート可能なベンダーに相談することがおすすめです。
NTTビズリンクでは、企業の技術継承の課題に適したデバイスを提案・支援する「スマートグラスソリューション」をご提供しています。
映像コミュニケーション分野における20年の実績から、デバイスの提供はもちろん、ネットワークの環境構築や運用支援も含め、お客さまの課題解決をトータルでサポートさせていただきます。
技術継承や人材育成などで課題を感じている方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。